講義一覧
※以下の日程・内容は現時点のものであり変更となる場合がございます。
※【1限】10時~12時10分 , 【2限】13時~15時10分 , 【3限】15時30分~17時40分
※会場は人数等の都合により変更となる場合がございます。
講師一覧

渋沢 寿一 氏(NPO法人共存の森ネットワーク 理事長)
1952年生まれ。1980年東京農業大学大学院修了。
国際協力機構専門家としてパラグアイに赴任後、長崎オランダ村、ハウステンボスの企画、経営に携わる。
現在は、NPO法人共存の森ネットワーク理事長。全国の高校生100人が「森や海・川の名人」をたずねる「聞き書き甲子園」の事業や、各地で開催する地域人材育成のための「なりわい塾」など、森林文化の教育・啓発を通して、人材の育成や地域づくりを手がける。
岡山県真庭市では木質バイオマスを利用した地域内循環経済「里山資本主義」の推進に努める。
明治の実業家・渋沢栄一の曾孫。農学博士。著書に「森と算盤」(大和書房)他
(以下、登壇の日付順です)

古川 明 氏(みずしま滞在型環境学習コンソーシアム 会長)
水島生まれ、高校まで岡山で過ごし、京都で大学生活を送った後に、現在のENEOS(株)「旧三菱石油」へ入社、一貫してエネルギー部門を歩く。サウジアラビア在住経験もあり、合併後の2000年には、水島港の東岸と西岸を繋ぐトンネル工事を手掛ける。転勤により20年前に故郷の水島に戻り、現在は、再生可能エネルギーを開発する会社の顧問や地元大学の講師を務める傍ら、水島のまちづくり活動などにも積極的に関わっている。
みずしま滞在型環境学習コンソーシアム 会長。高梁川流域学校 理事。

塩飽 敏史 氏(公益財団法人水島地域環境再生財団 理事・研究員)
1975年生まれ。2001年岡山大学大学院文化科学研究科行動科学専攻修了。同年4月財団法人(2011年11月より公益財団法人に移行)水島地域環境再生財団に就職。理事兼研究員。 瀬戸内海の環境再生を目指した海底ごみ調査及び、減量化に向けた提言、啓発活動に携わる。
(一社)高梁川流域学校 理事。

片岡 徹也 氏(NPO法人こうのさと 代表理事)
元小児科看護師。発展途上国での母子保健活動から、食と環境の重要性を実感。コロナをきっかけにNPO法人こうのさとを設立。食の自給や子どもたちが遊び学べる自然環境を保持増進している。
2023年にオルタナティブスクール「竹林のスコレー」を開校。企画した竹灯籠まつりでは廃校が懸念される過疎の村に1200人を超える来場者を得た。

伊藤 博暁 氏(岡山県立矢掛高等学校 コーディネーター)
2018年、高校魅力化コーディネーターとして広島県神石高原町に移住。2023年に地域での教育を支援するため、一般社団法人まなびぃを設立し地域全体で学びや教育について語る『学びと未来のフォーラム』を開催している。
今年度より岡山県立矢掛高校のコーディネーターに着任し、学校設定科目である『やかげ学』を改革中。高梁川志塾1期生。

佐伯 佳和 氏(HANAGI 杜の工房 代表)
新見市地域おこし協力隊「林業男子」として、林業の経験を積みながら、新見の木材を使い、家具の製作や商品開発を行う。その後、市内の林業事業体である(一社)人杜守へ入社、木工部門を担当し、オーダー家具類の製作を行う。
独立後、同市哲多町花木にて、『HANAGI 杜の工房』をオープン、家具および木工雑貨の製作、林業、無農薬小麦づくりなどを行っています。

大塚 小百合 氏(エシカルファッション協議会 理事)
1967年倉敷市生まれ。服飾専門学校卒業後、倉敷、岡山の企業でアパレル商品企画、デザインなどに従事。ハレマチ特区365では、おくりものマイスターとして岡山のものづくりを発信。
2022年よりエシカルファッション協議会の理事として、エシカルファッションを通じた持続可能な社会を実現するプロジェクトを推進。

中山 和幸 氏(株式会社テオリ 代表取締役社長)
岡山県倉敷市出身。大学卒業後、家具製造メーカーで経験を積み株式会社テオリに入社。
製造、工務部を担当し専務取締役を経て 2021 年7 月代表取締役就任。同 11 月に経営革新計画の認定、その後に竹集成材増産にむけ新規設備の開発を行い機械導入。
現在も新たな設備開発を計画中。想いを込めたものづくりに努め、地域の方々と共に持続可能な『竹循環型社会』の構築を目指す。

正田 順也 氏(下津井sea village project 運営責任者)
創業137年工務店を経営する傍ら全国組織古民家再生協会の岡山支部の代表として、古民家の調査や相談を受ける傍ら空き家セミナーなどで古民家の魅力発信を行う。
また、町おこし団体を立ち上げると共に、建築士・宅建士・古民家・空き家活用などの知識と町おこしでの移住支援を通じ真の不安(ひと、仕事、住まいなど)の解消する総合的な支援を行っている。
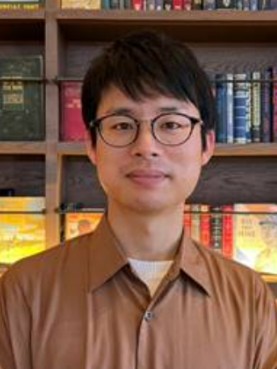
高山 和成 氏(一般社団法人ON-DO 理事長)
6歳で総社に移住して以降、自称「総社を5日間以上離れたことがない男」として、総社市を拠点に活動。17歳の時の師匠との出会いをきっかけに独立を決意。
2013年に家庭教師をはじめ、2015年学塾 誠和学舎を設立。
2022年6月に、小中学生の学習指導と地域人材の育成を行う一般社団法人ON-DOを設立、理事長に就任。地域団体の支援を行いながら、若手人材の育成に力を入れている。

中井 裕貴 氏(合同会社USHIMAROBI 代表)
大阪府出身。高梁川志塾5期生。2021年に瀬戸内市地域おこし協力隊として移住。
現在は、協力隊を卒業し、地域の体験アクティビティや周遊ツアーを販売する「せとうち旅物語」、泊まれる郵便局としてみんなで協力してリノベーションを行い2025年1月にオープンした「合同会社USHIMAROBI」代表を務めています。

友田 かおり 氏(2 1/2 ニトニブンノイチ 代表)
縫製工場勤務約20年を経て独立。現在は、余剰在庫布を活用し、小物や服を製作・販売する「保護布活動」に力を注いでいる。使われずに捨てられる布に、新たな役割を与える小さな商いを実践中。
高梁川志塾6期生。

蒲生 光宏 氏(イデアコネクト 代表)
イデアコネクト代表 倉敷市児島出身 倉敷市在住 主に動画を活用した採用、集客のお困りごとの解決サポートをしながら「緊急時にも生きていけて、手のかからない」をテーマに高梁川の水を使い小さな畑をしている。
高梁川志塾6期生。

猪野 遼介 氏(株式会社WHOVAL 取締役)
2008年、香川大学経済学部を卒業後、株式会社トマト銀行に入行。約9年間にわたり、法人営業・地域金融に従事し、地場企業との関係構築や経営支援に携わる。
2017年に同社を退社後、株式会社WHOVAL(本社:倉敷市児島)に参画し、取締役に就任。デニム製品の洗い加工・製造を主軸としたアパレル事業において、経営戦略・ブランド企画・地域連携に注力。
2024年には、WHOVALのコア事業以外の事業創出と地域資源の再価値化を目的に、Furious株式会社を設立。観光・文化・ものづくり分野を横断する新規事業や体験型コンテンツの企画・運営を手がけ、地域内外への価値発信を推進している。
現在は、企業経営の傍ら、地域プロジェクトや産官学連携事業にも積極的に関与。岡山県倉敷市児島エリアを拠点に、伝統産業と観光資源を融合した地域活性化をライフワークとして取り組んでいる。

佐藤 拓也 氏(株式会社さとう紅商店 代表取締役)
元高梁市地域おこし協力隊員。協力隊時代に赤い柚子胡椒と出会い、その衝撃的な美味しさから「この柚子胡椒で地域を盛り上げたい!!」と思い、紅の町「吹屋」の新たな特産品づくりに取り組み、吹屋の赤い柚子胡椒「紅だるま」が誕生した。
現在は佐藤紅商店代表を務め、特定の店舗を持たず、オンラインやデパートなどのアンテナショップなどで、販売を展開している。
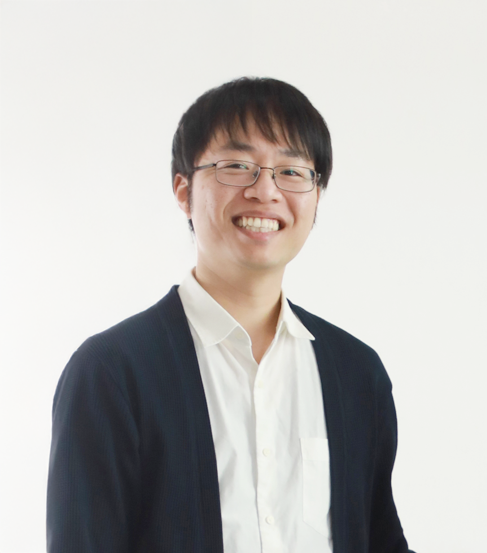
土屋 遼介 氏(TSUCREATOR 代表)
1992年生まれ 岡山県出身。倉敷芸術科学大学を卒業後、岡山・倉敷を拠点にフリーランスのウェブデザイナーとして多岐に渡り活動。
2021年に牛窓産檸檬を活用した岡山クラフトコーラ・ツチヤコーラの販売にも取り組む。

西垣 陽平 氏(一般社団法人みちくさコミュニティデザイン 代表理事)
2020年11月〜2024年10月まで高梁市地域おこし協力隊として活動。高梁市有漢町を中心に、日常的な多世代交流と地域連携教育の創出をテーマに地域活性に取り組む。
◯空き物件(元診療所)を改修したカフェ兼レンタルスペース「slow spaceみちくさ」の運営
◯IT難民のスマホ・PC活用支援
◯農業(ぶどう)
◯一般社団法人みちくさコミュニティデザインでの地域連携教育創造事業。

松原 龍之 氏(岡山経済新聞 編集長)
1977年倉敷市生まれ。2012年大阪よりUターン。父と不動産会社を経営しつつ、2014年WEB新聞社「岡山経済新聞」をスタート。「まち」をテーマにボランティア活動・カフェ経営・移住相談・畑作業を行っている。
一般社団法人高梁川流域学校 理事。

岡崎 遼太朗 氏(LAID-BACK DESIGN 代表)
1988年高知県生まれ。高校在学中に高知市の美術作家にデッサン・色彩技術を学びグラフィックデザインに惹かれる。倉敷芸術科学大学に入学。2011年大学卒業後、デザイナーとして活動している。
#LAID-BACK DESIGNデザイナー
#フリーペーパーSTAR*代表
#Canva公式クリエイター
#倉敷芸術科学大学非常勤講師

坂ノ上博史 氏(一般社団法人高梁川流域学校 代表理事)
1978年生まれ。倉敷市出身。早稲田大学第一文学部卒業。在学中よりSOHO&テレワークの調査研究と共同事業開発に取組み、経営コンサル会社取締役を経て、独立。300社を超える経営指導と30社を超える創業支援を担う一方、自らもサテライトオフィス『住吉町の家 分福』や、「高梁川流域学校」等のプロジェクトを手掛ける。
一般社団法人高梁川プレゼンターレ代表理事。一般社団法人MASC事務局長。

石原 達也 氏(PS瀬戸内株式会社 代表)
1977年岡山市生まれ。合同会社遠足計画・代表。PS瀬戸内株式会社・代表、みんなの集落研究所・会長等。
中間支援組織、まちづくり会社、社会的インパクト投資、災害支援、困窮者支援など、多様な組織の立ち上げや経営に参画。行政、企業、学校、NPO等と連携し、地域の社会課題を持続的に解決する「仕組み」づくりを専門とする。
<講座の日程、内容および講師は、都合により、予告なく変更となる場合があります。>


